枯れた技術の水平思考の内容は?

その具体的な内容とは、最先端ではない寧ろ使い古された技術を新しい角度から見直す事によって今までにない使い方を模索するというものであり、これによって新しい製品でもコストを抑えて生産する事ができますし、使い古された技術を使用しているのでバグや不具合に悩まされる心配もなくなります。
この哲学に基づく事よって横井軍平と任天堂は大ヒット商品を連発し今の地位を確立させていったのですが、現在でも任天堂は枯れた技術の水平思考に則った商品開発を行っていると言われています。
枯れた技術の水平思考に関する本は?
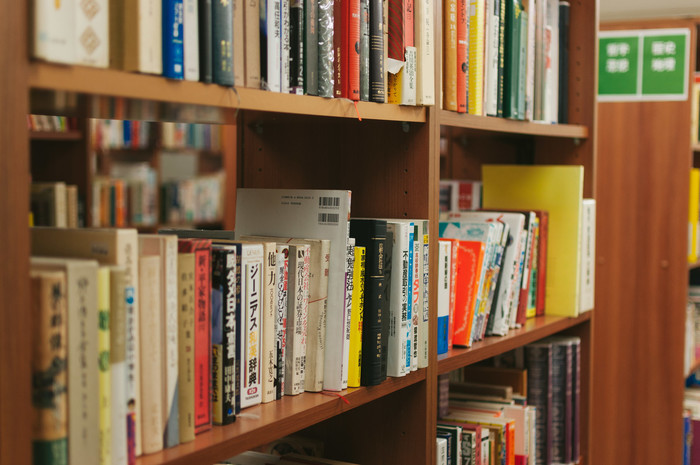
「世界の任天堂」を築いた発想力

何はともあれ非常に分かりやすい中身になっているので、ITやテクノロジーに精通していなくともキッチリと理解する事ができますし、枯れた技術の水平思考を具体例を通して学ぶ上では必読の1冊と言えます。
変に昂ぶったり飾ることなく、ニンテンドーの アナログゲームからデジタルゲームまで淡々と、 それでいて当時の熱気や横井さんの研究熱心さ を生々しく伝えてきてくれます。 作者さんの力量が素晴らしいです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1UC0MPBD1TEC4/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=4480432930
任天堂 “驚き”を生む方程式

なので横井軍平以外にも岩田聡など任天堂の中心的人物なども多数登場するのですが、横井軍平の人間関係や彼の枯れた技術の水平思考という哲学が今の任天堂にどういった影響を与えているのかといった事まで色々と秘蔵の話が知れるので、枯れた技術の水平思考に限らず包括的に学びたい人にはです。
なぜ任天堂が「DS」や「Wii」を世に送り出せたのかを、 そこにいたるまでの任天堂の社歴を含め、 前社長山内氏、現社長岩田氏、 宮本氏や横井氏らの思いを中心に書かれています。 経営理論や経営哲学ではなく、 その時、現場で何を感じ、何を考え、 それがどう商品という形になっていったのかがわかります。 「娯楽」「枯れた技術」「水平思考」「顧客の飽き」など いくつかのキーワードを元にして、 任天堂らしさ、 結果としての現在の任天堂の姿を理解出来ます。 素晴らしい会社、経営者、本でした。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R3THY232R6IRGJ/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=4532314631
任天堂ノスタルジー 横井軍平とその時代

また「任天堂 “驚き”を生む方程式」が今現在の任天堂に至るまでを取り扱っていたのに対し、「任天堂ノスタルジー 横井軍平とその時代」はゲーム&ウオッチやゲームボーイが販売開始された1980年代頃までしか取り扱っていませんが、その分横井軍平や彼の哲学にフォーカスした内容になっています。
横井軍平さんが、山内溥社長のもと、任天堂に就職し、どのようなものづくりをしてきたかという話。 任天堂が、どうしてゲームを作るようになったのか。 そして、最終的に、横井さんが独立して、亡くなるまで描かれています。 マリオやゼルダなどの話はありません。 ゲームウォッチの話で、ドンキーコングが出てくるくらいです。 「枯れた技術の水平思考」に興味があるならばぜひ読んでみてください。 今でも通用する内容です。 そして、任天堂のゲームと他のゲームを比較すると、その理念が生きていることを実感します。 「ゲームは白黒画面でも、十分おもしろいものができる」 「ゲームの進歩は、表現できる色を増やして、画面をキレイにすることではない」 最近、スマートフォンのゲームが流行していますが、 横井さんがこの現状を見たらどう思うのだろう、って考えます。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RH815DF3SJK70/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B00YTLRISI
枯れた技術の水平思考の実例は?

任天堂の実例は?
当時、電卓戦争により液晶画面という技術は枯れた物になりました。しかし横井軍平はその枯れた技術をこれまでとは全く違う方面から見る事によって、携帯ゲーム機に転用するという新しいアイデアを思いつきました。その結果、ゲーム&ウォッチは3800円という安い値段で量産する事が可能となり、日本に限らず世界的に大ヒットする事になります。
Nintendo Labo
このNintendo Laboも正に枯れた技術の水平思考の賜物と言えます。ダンボールという基本的に梱包などにしか使われない枯れた技術を見直す事によって、ゲーム機と組み合わせておもちゃにするという極めて斬新な使い方を発明しました。
- 1
- 2
初回公開日:2018年04月24日
記載されている内容は2025年03月06日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。










